行政書士試験の記述問題の難易度と対策
このページでは、行政書士試験の「記述問題」の難易度や対策等について記載しています。あくまで独学等による私の経験に基づく私見が内容の中心であることにご注意ください。
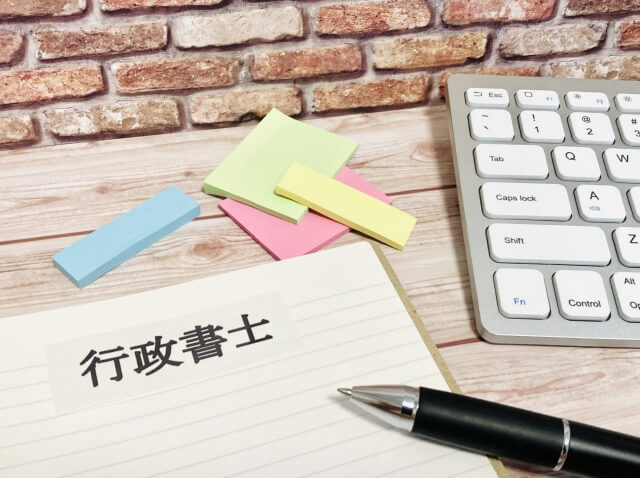
行政書士試験は、記述問題で点数を稼げるか?
行政書士試験の記述問題は、試験全体の点数(300点満点)の中で60点分とかなり配点が大きいことで知られています。(行政書士試験を受験する人で知らなかった人はこれを機会に是非知っておいてください。)
合格点が180点であることを考えると、1問4点である択一式問題でたくさん正解するよりは、記述問題で一気に得点できたほうが効率よく合格できるんじゃないか?と思ってしまいますよね。
果たして思惑通りに点数を取れるものなのでしょうか?
記述問題の内容・配点・過去の出題実績
行政書士試験の記述問題は、問われた内容に対して40字程度で解答を記述するという問題です。
毎年「行政法」1問、「民法」2問が出題され、各20点満点の3問合計60点の配点があります。下記表は過去10年間の記述問題の出題実績です。
| 行政法 | 民法① | 民法② | |
|
H26 |
公の施設・指定管理者★ | 詐害行為取消権 | 他人物売買 |
|
H27 |
原処分主義★ | 占有の性質の変更 | 嫡出否認の訴え |
|
H28 |
秩序罰★ | 契約不適合責任 | 財産分与 |
| H29 | 不適法による訴え却下判決 | 債権譲渡禁止特約 | 不法行為の損害賠償請求権の消滅時効 |
| H30 | 申請型義務付け訴訟★ | 制限行為能力者の相手方の催告権 | 書面によらない贈与の解除 |
|
R1 |
処分等の求め★ | 共有物の変更・管理 | 第三者のためにする契約 |
|
R2 |
無効等確認の訴え★ | 第三者詐欺 | 背信的悪意者 |
|
R3 |
行政指導の中止の求め★ | 債権譲渡禁止特約 | 工作物責任 |
|
R4 |
非申請型義務付け訴訟★ | 無権代理・相続 | 物権的請求権・債権者代位権 |
|
R5 |
差止めの訴え・仮の差止め★ | 抵当権に基づく物上代位 | 契約不適合責任 |
★:行政事件訴訟法 ★:行政手続法 ★:地方自治法
過去10年では「債権譲渡禁止特約」「契約不適合責任」が2回出題されている以外は、特に民法においては傾向ははっきりしておらず「どこから出題されるか絞ることはできない」状況と言えます。
行政書士試験の記述問題の採点方式
記述問題の満点は20点ですが、採点方式は公開されていないため不明です。
①解答の文章が短すぎる
②解答の文章の意味が通らない
③解答の論点がずれている
これらはいずれも「0点」となる可能性があります。
また、完璧な解答とは言えなくても「部分点」がもらえることもあり、もらえないこともあるようです。
①部分的にあっていても、結論を間違えている。
②部分的に間違えていても、結論はあっている。
これらはいずれも「0点」となる可能性があります。
少しでも「部分点」がもらえるように幅広く勉強したとしても、結果的に曖昧な知識ばかりだった場合は誤りが多くなり、0点ということもありえます。
行政書士試験の記述問題の難易度
記述問題は大別すると次のようになります。
①「条文を覚えていれば解ける問題」
②「条文を使えなければ解けない問題」
③「判例を知らなければ解けない問題」
→ 難易度は①より②③のほうが高くなる。
記述の難易度は、低めのときもあれば、けっこうな難問が出るときもあります。(択一式問題の難易度とバランスをとっているのかもしれません。)
大まかにいうと、条文の文言のみで解ける問題は難易度が低くなりやすく、条文を使って解いたり、判例の内容が問われる場合は難易度は高くなりやすいです。
(例:令和3年は難易度低め、令和4年は難易度高め)
記述問題は正確な記憶が要求される
下記は令和4年度の民法の記述問題です。
Aが所有する甲不動産について、Aの配偶者であるBが、Aから何ら代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して甲不動産をCに売却する旨の本件売買契約を締結した後、Bが死亡してAが単独で相続するに至った。CがAに対して、売主として本件売買契約を履行するよう求めた場合に、Aは、これを拒みたいと考えているが、認められるか。民法の規定および判例に照らし、その許否につき理由を付して 40 字程度で記述しなさい。
無権代理人を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反しないため、認められる。(44字)
※出題・解答例は「過去の試験問題 | 行政書士試験研究センター」より
解答例を見る限り、条文通りの文言や判例で使用された文言を用いて、意味の通る文章を40字程度(45字以内)で作成する必要があります。上記問題で言えば、判例に出てくる「信義に反しない」という文言が書けなければおそらく点数はもらえません。
大まかな内容の理解よりも、条文・判例等の「正確な知識(記憶)」が要求されているケースが多いと考えられます。
民法の記述の難しさ
条文の構成は「要件と効果」「原則と例外」のパターンでできていることが多いです。
薄く広く勉強している人は、例えば「要件と効果」の効果のみ、「原則と例外」のうちの原則のみしか記憶していないことなどが多いのではないでしょうか。条文問題では「2通り」の解答を要求されることも多く、薄く広くの勉強では対応が難しいです。
※判例については、基本的に条文に無い内容が判例となっているので、判例の内容を知らなければ全く解答が書けません。
行政書士試験の記述問題の対策
前述のように、条文等の「正確な知識(記憶)」が要求される傾向を考えると、膨大な範囲のある民法の記述において狙って点を取るのはかなり難しいのではないでしょうか。
| 各試験の民法の出題 | |
|---|---|
| 行政書士 | 択一式 9問 記述式 2問 |
| 宅建 | 択一式 10問 |
| 司法書士 | 択一式 20問 |
民法の記述の難易度が高いことに関係すると思われるのが、民法の範囲が膨大であるにもかかわらず、試験では択一が9問しか出題されないところです。これは宅建試験の10問、司法書士試験の20問よりも少ないです。
民法は、行政法に次いで力を入れて勉強すべき科目ではあります。しかし、全体を網羅するほどの出題数ではなく、特に「親族・相続法」の出題が択一で1問のみのため、民法の中では親族・相続法が手の抜きどころになっている方もいるのではないでしょうか。
そうすると、親族・相続法絡みで記述問題が出題されるとお手上げ状態です。(親族・相続法は過去10年に2回の出題実績あり)
行政法の記述問題20点満点を狙う
親族・相続法も手を抜かずに勉強するのはもちろん良いですが、行政書士試験自体の範囲がそもそも膨大なので、民法の記述対策用に力を入れる分を択一・選択式で21問出題のある「行政法」に入れたほうが、結果的に効率が良くなる可能性があります。
A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という。)が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の認可(これを「本件認可処分」という。)を受けて、土地区画整理組合(これを「本件組合」という。)が設立され、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分(これを「本件換地処分」という。)を行った。Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員であるところ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る。)を提起すべきか。40 字程度で記述しなさい。
本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効の確認を求める訴えを提起する。(40字)
※出題・解答例は「過去の試験問題 | 行政書士試験研究センター」より
上記は令和2年の行政法の記述問題です。
行政法の記述問題は、上記問題文中の「誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟を提起すべきか」のように具体的な解答の記述方法が指定されていることがよくあります。
とすれば、解答方法としては「〇〇を被告として、〇〇を対象とする、〇〇訴訟を提起すべき」の〇〇の部分に言葉を当てはめて記述すればよいことになります。解答の型ができてしまっているので、このパターンはしっかり知識を固めておけば十分20点満点が狙える問題です。
判決の拘束力(H21行政事件訴訟法)
事情判決(H22行政事件訴訟法)
即時強制(H23行政総論)
形式的当事者訴訟(H24行政事件訴訟法)
訴えの利益(H25行政事件訴訟法)
行政法の記述問題の過去10年出題実績よりも前の出題実績も合わせると、傾向としては「行政事件訴訟法」からの出題が多くなっています。
記述対策としてもやはり「行政事件訴訟法」を意識することにはなりますが、結局のところ「行政総論」「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」(+「地方自治法」「国家賠償法」「行政代執行法」)等を中心にしっかり勉強し、択一式問題を確実に解けるように知識を身に着けていくことが、記述問題においても一番の対策となるかと思います。
※やはり民法の記述でも点を取りたい、という方は、各資格学校等の記述講座や問題集を購入して学習されることをおすすめいたします。
