行政書士試験の択一式問題の難易度と合格のために手を抜く科目とは?
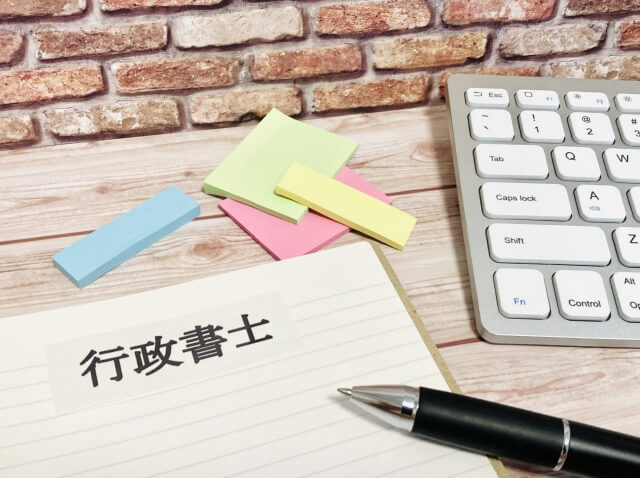
行政書士試験の択一式問題をどう攻略するか?合格するためにどのように勉強していくか悩むところですよね。
難なくこなしてしまう方もいるかもしれませんが、そういう方はきっとこのページは見ていないと思います。行政書士試験の勉強を始めて間もない方、勉強はしていても勉強方法や試験対策に悩んでいる方などを想定して書かせていただいています。
以下は、私の行政書士試験独学の経験から考えたに過ぎない勉強法・攻略法ですので、全くこの通りにする必要はありませんが、何かの参考になれば幸いです。
合格するためには、どのように得点すればよいか?
行政書士試験に合格するためにどのように勉強するかという点は、実際の試験で出題される問題をどのように得点していくかという点と関係があります。
「行政書士試験一般知識問題での足切りによる不合格回避対策とは?」
前提として「記述問題」「一般知識」をそれぞれどのように得点するかが重要となるのですが、上記記事でそれぞれ記述問題20点・一般知識24点を目標と記載させていただいています。詳細は記事をご覧ください。
行政書士試験は合格点が180点以上(300点満点)と決まっていますから、合格することだけを考えると180点以上取る必要はないということになります。
180点以上取れればいいということから逆算すると、
| 記述問題 | 20点 | 合計180点 |
| 一般知識 | 24点 | |
| 法令科目択一式 | 136点 |
180点に到達するためには、記述問題20点・一般知識24点の合計44点に加えて、法令科目択一式では+136点以上が必要です。(もちろん記述問題・一般知識で44点以上取れた場合はもっと少なくてよいことにはなります。)
法令科目択一式は184点満点(300点満点から記述問題60点満点・一般知識56点満点を引く)ですから、184点満点から136点以上を取るための勉強の方針を考えることになります。
合格するために、どのように勉強するか?
136点以上となると択一式で7割以上の正解が必要ですので、条件的にはなかなか厳しい数字です。この数字をクリアするためにどのように勉強すればいいのでしょうか?
もちろん全科目勉強すればいいんですが、行政書士試験は出題範囲が広く、一周するだけでも大変、そもそも出題範囲が曖昧でわかりにくい部分もけっこうあるんですよね。
「確実な知識が合格につながる」とよく言われるように、得点の確率を上げるには「確実な知識」を多く身に着ける必要があります。
結局のところ、勉強は「復習」が大事で、復習によって身に着けた知識が固まります。一度勉強したくらいでは数日後にはほとんど忘れてしまいます。闇雲に手を広げると結果的に曖昧な知識ばかりになってしまい、実際の試験ではほとんど答えがわからなかったということもあり得ます。
限られた時間の中で、復習の回数を多くして「確実な知識」を身に着けるには、勉強の範囲を絞ること、もっと言えば「勉強する科目を絞ること」が必要となってきます。
資格学校の講師さんたちは「ここはあまり深追いしなくていい」くらいは教えてくれると思いますが、全ての科目を教える立場なので、「この科目は勉強しなくていい」とまではおそらく言わないでしょう。
この記事では、独学ならではの視点で「手を抜くべき科目」をあえて言及してみたいと思います。
手を抜くべき科目・その1
「手を抜くべき科目」を決めるには、「出題範囲」「難易度」等について検討しなければなりません。この点から、まず、得点できない可能性が高いものは何なのか?を考えてみます。
基礎法学
基礎法学では、法律そのものの問題は基本的には出ません。過去問を解いて問題の雰囲気をつかむことはできますが、出題範囲が絞れず、何が出題されるかは不明です。
出題数は2問と少ないので、勉強時間はほかに回した方がよいでしょう。
行政法の一部
行政法の一部(2問)は、出題範囲が不明確です(むしろ「行政法全般」というべきかもしれません)。
本来、行政法とは行政に関する法律の総称であり、行政法全般となるとかなり出題範囲が広くなってしまいます。過去に国家行政組織法、国家公務員法、地方公務員法等から出題実績がありますが、これらが出題されるかどうかは不確実です。
そのため、確実に出題される行政総論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法(+行政代執行法)に多く勉強時間を回すべきかと思います。
※注:国家行政組織法は、行政不服審査法・行政事件訴訟法での「行政庁」に関係するため、組織図くらいは勉強しておいた方がよいでしょう。
手を抜くべき科目・その2
次に、得点できないというわけではありませんが、得点するためのコスパが悪いと思われるものを検討します。
親族・相続法(民法)
民法の中で親族・相続法は725条~1050条までとかなりのボリュームとなっていますが、行政書士試験の択一式問題では1問しか出ません。
債権法が4~5問出題されるのと比較すると、非常にコスパが悪いと言えます。民法では親族・相続法については手を抜き、他の法律に注力したほうが楽になるでしょう。
※注:行政書士の業務との関係では民法の他の法律よりむしろ重要な法律ですので、本来は勉強すべきです。
会社法
会社法については、手を抜くべきかどうかは少々悩みどころとなります。理由は、問題数が4問であり少ないとは言えないことと、問題自体の難易度が関係します。
会社法、地方自治法、憲法の比較
| 科目 | 出題数 | 難易度 |
|---|---|---|
| 会社法 | 4問 | 易~難 |
| 地方自治法 | 3問 | 普 |
| 憲法 | 5問+1問 | 普~難 |
「手抜き科目の候補」として、会社法、地方自治法、憲法を選んでいますが、これらに共通するのは条文(+判例)が多くボリュームがあるため、手間がかかり苦手科目となりやすいのではないか?ということと、手抜きすればかなりの負担減が見込めるということです。
憲法と会社法の比較
| 憲法 | 難問がよく出る |
| 会社法 | 容易に解ける傾向(条件あり) |
上記は、行政書士試験における憲法と会社法の問題の難易度の比較です(個人の感想)。
一見、会社法を勉強したほうが良さそうに思えますが、条件があり、具体的には司法書士試験(憲法・会社法いずれも出題あり)向けに勉強した場合は上記のようになります。力を入れて勉強すれば会社法を得点源とすることもできますが、行政書士試験では他の科目との関連性がそれほど高くない(行政とは無関係※ただし考え方に類似点はある)ため、4問の出題と考えるとどこまで時間を使って勉強すべきかが悩ましいです。
憲法は難問も出ますが、出題数は5問(択一式)+1問(多肢選択式)で会社法4問よりも多く、全体的な出題科目との関連性からやはり憲法の勉強は外せないと思います。
地方自治法と会社法の比較
| 地方自治法 | 行政法の記述問題に絡む可能性がある。会社法より条文は少ない。 |
| 会社法 | 記述問題では出題されない。条文が多い(民法以上のボリューム)。 |
地方自治法は、条文のボリュームはあるにもかかわらず、出題数は3問と会社法より少ないです。そのため手抜きしたくなる科目なのですが、記述問題で出題される可能性があります。
一方、会社法は記述問題での出題可能性はゼロです。全体的な出題科目との関連性からも地方自治法を勉強すべきでしょう。
会社法と商法の比較
| 商法 | 民法の延長のイメージ |
| 会社法 | もともと商法の一部であるが、商法とはかなり異なる |
商法・会社法と一括りにされていますが、法律の性質はかなり異なっており、商法は勉強すべきと考えます。
商法は、商人や商取引に適用される法律で、民法の延長のイメージで勉強できます。1問しか出題されませんが、範囲も広いというほどではなく(第三編「海商」以降はおそらく出題はされません)、難問も出ませんので、しっかり勉強していれば十分得点が計算できます。
一方、会社法は、もともと商法の一部とはいえ、主に会社の種類、設立、株式、役員、運営等のルールについての内容となり、民法とは全く異なります。
結論を言うと、会社法の勉強が負担になっている人は、手を抜いたほうが楽になるでしょう。
各科目における取るべき配点
「手を抜くべき科目」を決めたところで、私の考える各科目での取るべき配点について記載したいと思います。
| ①基礎法学 | 2問 | 0/8点 |
いきなりですが、基礎法学は手抜きするので2問不正解でも致し方ないです。
よく言われるのは「最初に難問をぶつけて受験生をビビらせる」ということです。解けない問題を出してビビらせようとしているだけなので、最初から解けないと思っていたほうが気が楽です。勉強は過去問を解くくらいにとどめておくべきでしょう。
| ②憲法 | 5問 | 16/20点 |
行政書士試験の憲法は、個人的にはけっこう難しい問題が多いと思います。勉強は憲法の条文、学説、重要判例が中心となりますが、「国民の権利及び義務」に関しては学説・判例、その他は条文問題が出題される傾向がありますので、難問以外は確実に得点して4問正解16点は取りたいところです。
| ③行政法A | 合計12問 | 44/48点 |
| 行政法総論 | 3問 | |
| 行政手続法 | 3問 | |
| 行政不服審査法 | 3問 | |
| 行政事件訴訟法 | 3問 |
ここは学習の中心です。「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」の条文は必ず全て勉強し、復習を繰り返してください。しっかり勉強すれば得点源となるはずです。また、記述問題で得点するためにも必要です。
| ④行政法B | 合計7問 | 20/28点 |
| 国家賠償法 | 2問 | |
| 地方自治法 | 3問 | |
| 行政法 | 2問 |
行政法Aと同じく学習の中心となりますが、ここの行政法の問題は国家行政組織法・国家公務員法などから出題されることもあり、出題範囲がはっきりとしません。そのため、国家賠償法・地方自治法で5問正解を目指すことになります。
| ⑤民法 | 合計9問 | 32/36点 |
| 総則 | 2問 | |
| 物権 | 2問 | |
| 債権 | 4問 | |
| 親族・相続法 | 1問 |
民法の問題の配分は多少変わることがあります。親族・相続法は手を抜くので不正解でも致し方ないです。
それ以外で8問正解したいところですが、難問も出ますので7問正解できればよしと言えるかもしれません(他の問題で正解する必要がありますが)。
| ⑥商法・会社法 | 合計5問 | 4/20点 |
| 商法 | 1問 | |
| 会社法 | 4問 |
商法は1問しか出ませんが、出題範囲はそれほど広くなく条文問題が多いので狙いどころです。
一方、会社法は手を抜くので4問不正解でも致し方ないです。出題されやすい「株式会社の設立」だけでも勉強しておけば+1問正解できる確率が高まります。
| ⑦空欄問題(多肢選択式) | 合計3問(12問) | 20/24点 |
| 憲法 | 1問(4問) | |
| 行政法 | 2問(8問) |
問題としては3問ですが、各問4つの空欄を20個の選択肢から選んで埋め、空欄1つ正解で2点となります。そのため、合計12問24点満点です。
判例や学説等が題材となるため難しい内容も出ますが、多肢選択式問題自体は文章理解の空欄を埋める問題と似ており、その場で考えることもできる問題ですので、できれば12問中10問は正解したいところです。
以上で+136点となりますが、基本的に得点を計算していない部分は全て間違えるとは限らず、1~2問は確率的に(勘で)正解できる可能性があるとお考え下さい。
問題を解く時間
行政書士試験は3時間(180分)・60問ですので、単純計算でマークシート記入も含め1問3分間の解答時間があります。しかし、記述問題や一般知識における文章理解に時間を使う場合、他の問題を1問3分間で考えている余裕はなくなります。上述の「手を抜く科目」では考える時間を短縮して、その分の時間を記述問題や文章理解へ回せるメリットがあります。
